加速抑制装置の効果は限定的です。何故かって?
加速抑制装置は、障害物センサーをつかって障害物を探知し、走行方向に障害物があれば、ドライバーがアクセルを踏みつけても、電スロ(電子スロットル)を電気的に抑制する装置です。
問題は、その障害物センサーは、100%信用できないということです・・・❶
それは、あくまで機械だから故障したり誤作動、誤認識したりするということであり、じゃ故障したらどうすんのということです。
ということと、
ドライバーがアクセルを意図的に踏んだか過失で踏んだかクルマは判断できない・・・❷
ということです。だから作動範囲が何故 0~15km/h なんですか?という疑問が湧いてきます。
何故 0~15km/h にしたかというと、それは:
15km/h以下ならドライバーが意図的にアクセルを踏む可能性が低いからと考えたと思います。
しかし、「踏み間違い事故」の94%は、走行中に発生(米国ノースカロライナ州警察データベースより)しているし、どの速度で発生したのかの統計はないものの「中高速域」からの踏み間違い事故は結構あると思います。つまり、15km/h 以上で踏み間違いが発生すれば、加速抑制装置は作動しません。
本来、AI(人工知能)が搭載されていない限り、運転に対する最終責任はドライバーにあります。だから:
ドライバーが何らかの主要操作をしたら、自動装置(加速抑制装置、自動ブレーキなど)は即時に解除されなければなりません。
アクセルペダルの踏み間違いは、ドライバーがアクセルを誤って踏むところから始まります。つまり、ドライバーがアクセルを踏む=機械はドライバーが運転制御をしていると解します。
∴ 加速抑制装置の効果は、限定的と思います。
次の動画は自動ブレーキに関することです:
動画出典:youtube
自動ブレーキを過信しないでって、どういう意味かな~? 確かに自動ブレーキはぎりぎりの距離にならないと効かないようになっています。これは運転者の自動ブレーキに対するオーバーリライアンス(過剰信頼)を防ぐためだそうです。
でも人間って便利なものに慣れちゃうと・・・慣れちゃうと、つい頼りがちになります。
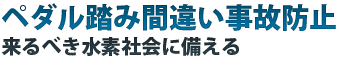




コメント
トラックバックURL