昨日の続きです。さて、MD11の成田空港事故です。この日わたしは友人と千葉県大多喜町でゴルフをするために千葉に向かう途中でした。大変風が強く、アクアラインが閉鎖になるかどうか心配するほどでしたが、幸い速度50km/h規制で済んで無事渡り終え、ほっとしたところでしたが、7時のニュースでこれを知りました。ところで余談ですが、アクアラインを通れないとわたしの居住する横須賀から千葉に渡るのには2通りの方法しかありません。久里浜~金谷へフェリーを使う方法と京葉道路や湾岸道路を使って東京を抜け、陸周りで行く方法です。このうちフェリーは風が強かったりするとすぐ欠航になります。陸まわりは大変な時間がかかり、アクアラインを通るルートより2倍の時間は堅いです。さて、事故の概要は以下の通りです。:2009年3月23日フェデラル エクスプレス(アメリカの宅急便会社です)80便は、その中国でのハブ空港となっている広州白雲国際空港を夜中に出発し、午前6時49分成田の滑走路34L(レフト)に着陸しようとしていました。強風の中(成田航空気象台の記録では平均14m/sec=約28ノット、最大20m/sec=約40ノット北風、事故直前では17m/sec=約34ノット)右主車輪から激しく1回目の接地、さらに2回目のバウンドで前輪から接地し、3回目の接地で左主翼端を滑走路に接触させて左主翼が折れ、左側に横転して仰向けとなって滑走路わきの草地で大破炎上しました。機長(54歳男性 アメリカ海兵隊出身F4ファントムパイロット)、副操縦士(49歳男性 アメリカ空軍出身C5など大型輸送機の機長)は、操縦席に逆さづりの状態で見つかり火災鎮火後に救出されましたが、胸部打撲(機長)及び焼死(副操縦士)で死亡が確認されました(MD11は2人乗務、航空機関士なし)。わたしのパイロットとしての経験からいって、接地のときに激しくバウンドするのは、前輪からついてしまったときです。事故調が公開したCVR(コクピット ボイス レコーダー)では、事故時にどちらが操縦していたのか明らかではありません。わたしの推測ですが、成田管制塔と交信していたのはキャプテンですので、恐らく副操縦士が操縦していたのではないかと思います(操縦していない方が管制機関との交信を行います)。機長は54歳、総飛行時間8,132時間、副操縦士は49歳、総飛行時間5,248時間ですぐキャプテンという飛行時間です。この飛行時間は凄いです。つまり、どちらが操縦していたとしても、共に最高の操縦免許(定期運送用操縦士)を持ち、相当の操縦経験を持つパイロットが、最初の接地で飛行機が跳ねたとしても、次の接地で操縦桿を押す操作(前輪からの接地となる)は絶対にしないということはパイロットとしての常識です。あり得ないことです。しかし、現実はそうなっています。ということは、パイロットが操縦桿を押さなければならないことが発生したということです!!前輪から接地したことがこの事故のキーポイントです。わたしはMD11の致命的な欠陥、機体の勝手な、急激な頭上げが発生したのだと思います。着陸接地のときです。パイロットは思わず思いっきり操縦桿を押した!!オーバーコントロールになったと思います。前輪から接地となりました。この日は強風であったので、失速する危険があり、通常の着陸速度の2割増しくらいで着陸します。重さにもよりますが、MD11の場合、大体130~140ノット(約250km/h)くらいですので2割増しは、168ノット。事故調の分析によれば、166ノット(約300km/h)で接地したとあるのでやや速いかなと思いますが、ノーマルな接地の範囲だと思います。後で聞いたらMD11の場合はこれが正常とのことです。
さて、他はどんな同種事故があるのでしょうか? 1997年7月31日午前1時32分頃フェデラルエクスプレス14便は、ニュージャージー州ニューアーク空港の22Rへ着陸しましたが、一度接地した後バウンドし、次の接地で右に傾きながら滑って裏返しになりました。気象条件は通常だったと報告されています。1999年8月22日、チャイナエアライン(中華航空)のMD11、642便は、タイ バンコク発香港経由台北行であり、台風10号が接近している中、午後6時43分頃、香港に到着し着陸しようとしましたが、右主翼を滑走路に接触させたあとそのままロールして左側の主翼ももぎ取られて発火し胴体部分だけで背面になって停止しました。この他、裏返しにはなっていませんが、1999年10月17日には、上海を出発しフィリピンのスービック ベイ国際空港に着陸しようとしたフェデックス87便が、滑走路で停止出来ずオーバーランし、海に突っ込んで大破し水没しました。2009年3月末までにMD11は6件の全損事故を起こしています。中途半端なハイテク化(最初から設計せずに既存の機体を改修させた)が結局DC8から続いてきたマクダネルダグラスをも消滅させてしまいました。さて、日本の事故調は、成田のフェデックス80便事故を調査して事故報告書をまとめました。主管調査官はC調査官。このひとは航空大学の実科教官を長くされたひとで大型機の経験はありません。ケーブルテレビを見ておられる人はナショナル ジオグラフィック チャンネルの『MAYDAY』という航空事故ばかりを取り上げた番組をご存じだと思いますが、この事故は、そこでも取り上げられました。ここでは、DFDR(飛行記録装置)の解析から20フィートでフレアを開始しているとあります。約2秒で接地ですのでフレア(着陸直前の機首上げ)が遅かったと。大型機では、高度1000フィートから自動音声で、1000、500、100、50、30、20、10と聞こえます。その間隔は低くなればなるほどゆっくり読み上げられます(機首上げフレアをして速度を殺していくため降下率がゆっくりになる)。しかし、CVR(コクピット ボイス レコーダー)に残った音声では、読み上げが逆に一定間隔かむしろ速くなっています。フレアが遅くなったその理由は、所謂『風の息』で速度が抜けたり出すぎたりするので、速度を維持するために機首を押さえて遅くなったのではないかとしています。実際、飛行機を操縦していてウインドシアなどで急に速度が低下すると、足下の床が抜けたような感覚に襲われます。エアポケットにはいったようにフワッと機体が下がる感じ。ホントに頼りなくなります。だから機首をわざと押さえたという意見には賛成です。飛行機に乗り込んでいればいるほどそうなります。 乗務前の機長、副操縦士の行動を克明に調べて、とも乗務による睡眠不足と疲労があったためフレアが遅れたのではないかともしています。また、副操縦士が1回目のバウンド後操縦桿を押したこと(DFDRに記録が残っていました)は、主車輪が滑走路についているという前提条件の下、早く前輪をつけたかったからとの説明になっていました。早く前輪が着けば早く停まれますので。しかし、アメリカ空軍に長く在籍し、C5(アメリカ空軍の超大型輸送機)の機長も務めたであろうパイロットがいくら疲れていてもそんなことをするはずがないです。絶対しない。事故調は、バウンドしたときを予想するコクピットからの視野CG動画を製作し、前輪を早くつけたいので操縦桿を押したとのストーリーを正当化させようとしました。たしかにそのCG映像では、主車輪がついているかついていないか判らないように緩やかな機首上げをわざ(!)と作ってあります。バウンドの程度はいくらでもお手盛りできるわけですから。DFDRの記録からどのくらいのピッチアップになり、どのくらいバウンドしたか明白に判るはずですが。わたしが感じることは、このことには、調査チームに途中から参加したアメリカNTSBの調査官ポール ミセンチェク セニア(Paul Misencik Sr.)の意向が強く反映されているのではないかと思います。C調査官は、着陸前に自動音声が出ることさえ知らなかったと思います。ましてや着陸のときバウンドしたMD11のコクピットから外がどのように見えるかについても知らないはずです。ミセンチェク調査官は、1967年イースタン航空(倒産して今はもうありません)入社1991年倒産時まで査察操縦士(パイロットのチェッカー)を務めています(多分ロッキードL1011機長)、エバグリーン航空(香港の貨物便会社)、USアメリカ エアウェイズなどで機長を務め、1996年NTSBのパイロット担当部門のチーフとして採用されました。(わたしの英語の先生だったひとの義理のお父さんで、全米でも有名なイースタン航空の看板機長だったビッケン機長も同様にFAA(連邦航空局)に再就職してボーイングB757、B767のパイロット試験官を務めておられますが、アメリカの官側(FAAとかNTSBとか)の航空界は倒産したイースタン航空出身者が多く働いています。ちなみにイースタン航空は労働争議の果て倒産いたしました)ともあれ、ミセンチェック調査官は、MD11の経験があるかどうかわかりませんが、マクドネルダグラスとは深く親交があります。NTSBが送りこんできた人ですから、MD11の経験が長いのかもしれません。しかし、人が悪いかもしれませんが、考えようではMD11を延命させるためにアメリカから送りこまれた人かもしれません。巧妙に《パイロットミス原因》を誘導しています。それは成功したようです。現にFEDEXでは2016年現在未だ生きながらえて使っているのですから。大型機の経験がないC調査官を丸め込むのは簡単だったと思います。日本にもいくらでもMD11経験者のキャプテンがいるのですから日本乗員組合連絡会議と手を取り合ってそういうキャプテンを専門委員に任命すればいいのです。例えば高本孝一MD11機長などです。まあ、事故調は彼らからは全く信用されていないですけれど。わたしは、これだけの経歴をもったパイロットがどんなに疲れていても、バウンドして(パイロットはバウンドしたことが判っていたはずです)前輪を早くつけようとして操縦桿を押すということは絶対にないと思います。浮いたときに滑走路からズレそうであれば、すべてのパイロットが躊躇なくゴーアラウンド(着陸復行)を決意します。エンジンは問題ないわけですから。そんなことは29年間も空を飛んできたミセンチェック調査官には判っていたはずです。この事故の原因は、2回目の接地のときに前輪から接地したことであり、それは機体が勝手に激しい「ピッチアップ(機首上げ)」を起こしたからであり、パイロットは本能的に操縦桿を押さえた(押さえ過ぎた)からです。そしてこのようなことが発生したのは、MD11が燃費をケチって水平尾翼を小さくし、その不安定さをガンタレ(業界用語=屑、ジャンク品の意味)コンピューターで補正しようとしたからです。このようなことはいままでいくらでもありました。初めてのことでもありません。航空機の開発には巨額のお金が必要です。MD11も200機世の中に出したわけですから。成功とはいえないまでも、捨てるには投資が大きすぎます。いま、東京オリンピックに絡めて猫も杓子も自動運転自動運転とお念仏のようです。しかし、飛行機も自動車もひとの命をのせて高速で移動するものです。パソコンと違って、クラッシュやバグが許されません。MD11のように目先の利益を追求して未熟なコンピューターを搭載するとこういうことになります。そして、未熟だと解っていても、投資したお金が巨大であればあるほど途中で捨てられないのです。まるで『もんじゅ』のようではありませんか?2016年9月20日のニュースで知ったのですが、『もんじゅ』は廃炉決定かと思っていましたが、『政府として検討する』と菅官房長官が声明を発表しました。悪あがきにしかみえませんね。だだ、今までかけてきた金一兆円を考えると、税金ですから、簡単に間違っていましたといえない部分があるのでしょうね。賢い安倍=菅コンビですから、正しい判断を示すことでしょう。2016年9月18日の試算では、もんじゅの再開には、5800億円くらいかかるともニュースが報道されていました。ますますMD11と似てきました。MD11は旅客機から貨物機へすることでかろうじて生きながらえましたが、もんじゅはどうにもならないでしょうね。
動画出典:youtube
MD11(左)とDC10(右)尾翼の違いを見てください 出典:Wikipedia
FEDEX80便成田空港事故 出典:Wikipedia
FEDEX14便香港事故 出典:Wikipedia
ポール ミセンチェク Sr.NTSB事故調査官 出典:http://www.blueheronbookworks.com/paul-misencik–sr..html
アメリカの日本乗員組合連絡会議にあたるALPA(エアラインパイロットアソシエーション)でALPA定期刊行物に漫画(カートゥーン)の絵を長く描き続けていました。才人ですね。
FEDEX MD112016年の今はB777Fにとって代わられだんだん機数が少なくなってきています 画像出典:Wikipedia
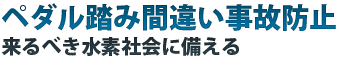









コメント
トラックバックURL