今(2017年6月23日)を去ること2か月前のNHKためしてガッテン『大型連休の前に「家族を交通事故から守りたいSP」』でわたしの恩師九州大学名誉教授松永先生が『ペダル踏み間違い事故』についてご意見を述べられていました。わたしは先生のご意見と次の3点で違った意見を持っています。
1.ペダル踏み間違いの発生原因
(松永先生):アクセルからブレーキを踏むべきところで、携帯の着信音など気を削がれるようなことや何か咄嗟のことが起きることでペダルの踏み間違いが起こると述べておられます。
(大野):この形態の事故の96%は実に他愛のない、緊急性や突発性のない状況で発生しています(米国ノースカロライナ州警察データベース 踏み間違い事故前走行状況)。例えばコンビニ等の平面駐車場に駐車するときなど、ブレーキが必要な場面でアクセルを踏むことから事故は始まっています。
わたしはこのため、『ペダル踏み間違い事故』ではなくて『ペダル踏み換え忘れ事故』と呼んでいます。
2.防止法
防止法その1:
(松永先生):先生は「ためしてガッテン」のなかで『アクセルはゆっくり踏む癖をつけましょう』と言っておられます。そうすればペダルの踏み間違いが起こってもクルマはゆっくり発進するのでブレーキを踏む余裕が生まれるといっておられます。
(大野):それはあくまで運転者がアクセルを操作する要領についていっておられるだけで実際の状況とは著しい乖離があります。
車体を停止乃至は減速させるためにブレーキを踏む強さで誤ってアクセルを踏むから車体の急加速が生まれると思います。
防止法その2(運転者は何故アクセルから足を離せないか?):
(松永先生):ノーコメント
(大野):イギリスポーツマス大学のジョン・リーチ博士が言っておられるようにこれは死の恐怖に曝された人間(運転者)の『生理的な反応』であるとする学説に全面的に賛成です。足を突っ張って離せなくなるのも生理的な反応です。また、暴走中人間の脳は『機能不全』に陥ります。脳が機能不全に陥ると何も考えられなくなります。
3.踏み間違い実験について
(松永先生):運転者に外乱(携帯着信音など)を与えれば再現可能。『ためしてガッテン』で実施された実験では段ボール箱に突っ込んでいましたが暴走には至りませんでした。
(大野):暴走は無意識での踏み換え忘れから始まり、このことは再現不能です。したがって暴走の再現実験はできないと思います。
画像出典:Wikipedia
動画出典:youtube NHKためしてガッテン 踏み間違いは33:30くらいからです。
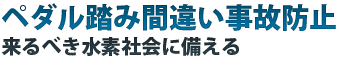








コメント
トラックバックURL