おフランスというのは、金に汚い国です。「無理」を無理やり押し通すのも好きです。以下時事通信の記事をYahoo配信で:
な~にが問題提起じゃっ!!
ゴーン事件で仏「問題提起」
ゴーン事件で「問題提起」=仏外相、河野氏に伝達
【ディナール(フランス)時事】河野太郎外相は5日、フランス北西部ディナールで開かれている先進7カ国(G7)外相会合に合わせ、ルドリアン仏外相と会談した。 日本の外務省によると、日産自動車前会長のカルロス・ゴーン容疑者が再び勾留されたことに関し、ルドリアン氏から河野氏に「問題提起」がなされたという。具体的な内容について外務省は明言を避けた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
だそうです。次は強欲経営者のお話し、新潮社記事から:
「ゴーン」だけではない「強欲経営者」列伝
フォーサイト-新潮社ニュースマガジン
杜 耕次
東京地検特捜部による日産自動車会長、カルロス・ゴーン(64)の逮捕が世界に衝撃を与えている。報酬の過少申告に加え、海外子会社の資金の私的流用などへ疑惑は広がり、事実ならば、その強欲さは巨大企業のトップとしては前代未聞。山高ければ谷深し――。
「日産再生の立役者」との評判が高かっただけに、金銭スキャンダル発覚後の風当たりの厳しさは当然だろう。
だが、実績に見合うとは思えない破格の役員報酬を得ている例は他にもある。日本では2例目という司法取引を使った特捜部の異例の摘発には、初心(うぶ)な日本企業をカモにする外国人経営者を一網打尽にする狙いも秘められているのかもしれない。(敬称略)
トヨタの報酬の「7倍」
ゴーンの突出した高額報酬はかねてヤリ玉に上がっていたが、最初に兆候が表れたのは、親会社の仏ルノーから日産に送り込まれてから2年後の2001年6月21日だった。
この日、ゴーンは株主総会後の取締役会で社長兼最高経営責任者(CEO)に着任。名実共に日産のトップとして最初に打ち出した施策が、役員報酬総額の上限の引き上げだった。
それまで10億8000万円だった上限額を15億円に引き上げただけでなく、併せて9年ぶりに役員賞与を復活させ、8人の役員に総額2億6000万円を支給することを決定した。「目標を達成した際のインセンティブが働く仕組みにする」というのがこの時のゴーンの説明だった。
確かに、直前の連結業績は最終損益が4期ぶりに黒字転換した。1998年3月期に140億円、1999年3月期に277億円、2000年3月期に6844億円をそれぞれ最終赤字として計上。3年間で累計7261億円という長い赤字のトンネルから脱し、ようやく2001年3月期に3311億円の黒字へと「V字回復」したところだった。
ただ、人に譬(たと)えれば、重病がようやく癒え、なんとか自立歩行を始めた段階。株主やアナリストの間では「役員報酬の引き上げは時期尚早」との見方が多かったものの、結局は「一丸となって危機を乗り切った役員に報いるのも今後の士気向上のために必要」(当時の日産関係者)という“ゴーン支持派”の意見が通ってしまう。ところが、月日の経過と共に日産の高額報酬は役員を一丸にするものではなく、特定の個人、つまり絶大な権力を振るうようになったゴーンに集中的に支給されるものであることが明らかになっていく。
最初に大きく批判を浴びたのは、2007年3月期に日米市場での販売不振により、ゴーンのトップ就任以来初めて減益になった時だった。連結営業利益、最終利益ともに前期比11%減となり、マスコミは「“ゴーン神話”に陰り」と書き立てた。
批判の高まりを受けてゴーンは前期に取締役7人に対して総額3億9000万円を支払っていた「役員賞与」をこの期はゼロにすると表明したが、「役員報酬」については前期と同じく総額25億円とした(「役員報酬」の上限は2001年に15億円に引き上げられた後も増額が続いていた)。 しかも、支払いの対象となる取締役の数は前期の11人から9人に減っていたため、1人あたりの受給額は増える計算だった。
当時、日産の1人あたりの役員報酬額は、トヨタ自動車の7倍と言われた。2007年3月期の両社の連結業績を比べると、売上高はトヨタの23兆9481億円に対し、日産は10兆4686億円と半分以下、最終利益はトヨタの1兆6440億円に対し、日産は4608億円と3分の1以下。トヨタの「渋チン経営」は脇に置くとして、これほどの劣勢にもかかわらず7倍の報酬を役員に与える日産の大盤振る舞いが、株主の批判を浴びるのも無理はなかった。
仏政府の反対も押し切り
ただ、「高過ぎる報酬」が日産の役員全員に行き渡っていたわけではない。同社では、役員報酬の総額は取締役会の協議事項だったが、振り分けはトップであるゴーンの専権事項だった。2007年当時、ゴーンの取り分は総額の6割以上で、その金額は「15億円を超えている」(同社関係者)と言われていた。
次に大きな批判が沸き起こったのは、2010年6月の株主総会。リーマン・ショックの影響で2009年3月期に2337億円の連結最終赤字を計上。2010年3月期は424億円の黒字に転換したものの、2008年3月期に10兆8242億円あった売上高が2009年3月期は8兆4370億円、2010年3月期は7兆5173億円に落ち込み、加えて10年ぶりの無配に転落した。そんな苦境下にもかかわらず、ゴーンの2010年3月期の報酬が日本企業で最高額の8億9000万円だったことから、株主は猛反発した。
株主の批判に対し、ゴーンは「日産は一般の日本企業とは違う。同規模のグローバル企業に比べればまだ安い」と釈明。だが、ゴーン以外の役員をみると、ポルトガル生まれのカルロス・タバレス(1億9800万円)、英国出身のコリン・ドッジ(1億7600万円)の2人の外国人副社長、最高執行責任者(COO)の志賀俊之(1億3400万円)など、いずれも2億円に届かない水準(肩書はいずれも当時)。ゴーンの突出ぶりだけが目立っていた。 おまけに、2005年5月に親会社ルノーのCEOも兼務するようになったゴーンには、そのルノーから124万ユーロ(当時の為替レートで約1億3800万円)の役員報酬も支払われていた。日産の8億9000万円とその6分の1以下のルノーの報酬との大きな落差について突っ込まれたゴーンは、「ルノーは外国人が少ない純然たるフランス企業。(124万ユーロは)一般的なフランス企業と同水準の報酬だ」と強弁。子会社の日産が「グローバル企業」であり、親会社のルノーが「一般的なフランス企業」という釈明は、それだけですでに論理が破綻しているように聞こえた。それでもゴーンに対する日産の高額報酬は変わらず、大半のマスコミは「名経営者」と持て囃し続けた。
だが、この時の高額報酬批判がゴーンにはこたえたに違いない。今回、特捜部が金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑とした報酬の過少申告の期間は、2011年3月期から2015年3月期まで。つまり、2010年6月の株主総会で批判を浴びた次の決算期からの5年間に実際には約99億9800万円の報酬を受け取りながら、有価証券報告書には約49億8700万円と虚偽の記載をしたというわけだ。
ルノーはフランス政府が約15%出資する筆頭株主であり、経営陣の高額報酬に対して目を光らせている。特に2012年に大統領に就任したフランソワ・オランド(64)、2017年就任のエマニュエル・マクロン(40)と2代続いた左派政権は、株式を長期保有する株主の議決権を2倍にできる「フロランジュ法」を盾に取り、ルノーへの経営関与を強めようとした経緯がある。
ところが、そんな政府の圧力を無視するように、ルノーから受け取るゴーンの報酬はその後大幅に増加。その額が725万ユーロ(当時の為替レートで約8億8300万円)にまで膨らんだ2016年には、4月のルノーの株主総会で批判が噴出し、報酬を決める議案に筆頭株主の仏政府をはじめ54%の株主が反対に回った。ただ、その採決には拘束力がなかったため、ゴーン側が業績連動部分の減額を申し出てお茶を濁す結果になった。結局、翌年の株主総会でも議案で提示されたゴーンの報酬は700万ユーロ(同約8億5800万円)と高止まりし、仏政府は反対の姿勢を貫いたが、個人株主の賛成でかろうじて否決を免れている。
ソニー:8600億円赤字でも報酬20億円超
一方、ゴーンが得てきた日産からの高額報酬が日本企業に伝播した例もある。
代表格はソニー。2003年、自らを「ソニーで最初のプロフェッショナル経営者」と称していた会長兼CEOの出井伸之(81)は、ゴーンにソニーの社外取締役就任を依頼。「30秒で応諾してくれた」と出井は後に喧伝した。
出井は2005年に業績不振の責任を問われて経営トップの座を追われることになるが、その翌年の2006年に出版した著書『迷いと決断』(新潮新書)でこんなことを述べている。
〈私はソニーに報酬委員会を設置して経営幹部の報酬を決定する仕組みを作りました。(中略)グローバル企業の経営者に支払われるべき報酬はグローバルな水準を考慮されてしかるべきだと考えたからです〉
これは、高額報酬の批判を浴びたゴーンが釈明した際に引用した「グローバル企業」の基準にぴたりと重なる。また、出井は同書でこうも述べている。
〈日本の企業が経営者にそれほど報酬を支払わないのは、やはり経営を『技術』として評価していないからです〉
周知のように、出井の後継者として2005年6月に会長兼CEOに就任したハワード・ストリンガー(76)が、2009年3月期から2012年3月期までの4年間に総額8560億円に達する連結最終赤字を計上しながら、この間少なくとも20億円以上の報酬を受け取っていたことが当時問題視された。
ストリンガー時代のソニーの業績不振の一因は、出井がトップ在任中に次世代の収益の柱を築けなかった「失政」にあると言われていた。足元の業績を見るのは最高財務責任者(CFO)の責任であるが、5年先、10年先の収益の布石を打つのがCEOに課された責務であることを出井は認識していなかったようだ。
武田薬品:「無謀な買収」でも報酬32億円
高額報酬を受け取る合理性がどうにも理解できないケースは他にもある。
武田薬品工業の社長兼CEOであるクリストフ・ウェバー(52)は、2016年3月期から2018年3月期までの3年間に、合計31億7000万円の役員報酬を受け取った。これに対し、ライバルであるアステラス製薬の社長(当時、現会長)、畑中好彦(61)の同期間の役員報酬の合計額は、7億5100万円と4分の1以下にとどまる。
両社の業績を比べると、この3年間の連結営業利益は武田の5285億円に対しアステラスは1.4倍の7231億円、最終利益も武田の3820億円に対しアステラスは1.5倍の5771億円と、いずれもアステラスが大きく上回っているにもかかわらず、である。 武田の前会長(現相談役)、長谷川閑史(72)が「グローバル化推進の切り札」として英グラクソ・スミスクラインのワクチン部門社長などを務めていたウェバーをスカウトし、社長に据えたのは2014年6月。以後、経営会議メンバーの大半を外国人(現在14人の経営会議メンバーのうち日本人は3人)が占めるなど、武田の外形的なグローバル化は進んだものの、業績は振るわないままだ。
そんな中、武田は今年5月8日、アイルランドのバイオ医薬大手シャイアー社の買収で合意。実現すれば、総額460億ポンド(約6.6兆円)という日本企業としては過去最高の巨額のM&A(合併・買収)となる。株式時価総額が3兆5571億円(11月20日終値)の武田にとってハイリスクであることは言うまでもなく、さらに買収価格と被買収企業(シャイアー社)の純資産の差額である「のれん代」がざっと3兆円と見られることから、アナリストたちからは「無謀な買収」との声が次々に上がっている。
シャイアー社の2017年12月期の業績は、売上高が1兆6520億円、最終利益が4654億円。武田の連結業績にこれが加われば、確かにライバルのアステラスに大きな差をつけることができる。
だが、会計評論家の細野祐二によれば、最終利益4654億円を前提にROE(株主資本利益率)8%として収益還元方式でシャイアー社の適正価値を算出すれば約5.8兆円となり、武田の買収提示額を1兆円近く下回る(『週刊エコノミスト』2018年6月5日号)。
絶対額でも、理論値でも「高い買い物」であることに相違なく、場合によっては武田を破綻の瀬戸際に追い込む可能性も否定できない。ただでさえ、高額の報酬を支払っているCEOにこんなイチかバチかのギャンブルをされては、社員も株主もたまったものではないと思うのだが。
セブン&アイ:日本人社長の24倍
もう1人、役員報酬金額が突出しているのが、セブン&アイホールディングス(HD)取締役のジョセフ・マイケル・デピント(56)。2016年2月期から2018年2月期の3年間の役員報酬合計額は、64億8500万円。デピントは米セブン-イレブン社長を2005年から務め、セブン&アイHDの前会長兼CEO(現名誉顧問)の鈴木敏文(85)の信頼が厚く、「大のお気に入り」と言われてきた。
しかし、社長の井阪隆一(61)の2018年2月期の役員報酬が1億1100万円とようやく1億円を超えて開示対象になったのに対し、デピントの同期の報酬は24億300万円と実に24倍。デピントの報酬の出処は自らが社長を務める米セブン-イレブンだが、親会社であるセブン&アイHDの決算書で見ると、北米事業の2018年2月期の営業利益は756億円で、セブン&アイHD全体の営業利益3917億円の2割に満たない。
高額報酬を一概に否定するつもりは毛頭ないが、有能な経営者を子会社のトップにスカウトするにしても、事業が軌道に乗れば後継の人材に託す体制に移行するのが合理的な経営の常道である。親会社のトップの20倍以上の報酬を子会社の社長に払い続けるのはどう見ても不自然で、明らかに「もらい過ぎ」だ。
1989年にソニーが48億ドル(当時の為替レートで約6800億円、負債継承分も含む)で米コロンビア映画(現ソニー・ピクチャーズエンタテインメント)を買収した後、共同CEOの座に就いたピーター・グーバー(76)とジョン・ピーターズ(73)は放漫経営の限りを尽くし、浪費した金額は10億ドルとも20億ドルとも言われた。その実態を描いたジャーナリストのナンシー・グリフィンとキム・マスターズの共著『ヒット&ラン――ソニーにNOと言わせなかった男達』(エフツウ、1996年刊)は、日米でベストセラーになった。
「お人好しで物分かりが良い」という日本企業の“グローバル”なイメージがバブル全盛期の約30年前とほとんど変わらないことは、内部告発があるまでワンマン経営者の暴走を止められなかった今回の「ゴーン事件」が象徴している。したたかな外国人経営者による“ヒット&ラン”は、今でも、どこにでも、起こり得るのである。(2018年11月)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これって絶句するよね~。みなさんどう思いますか?
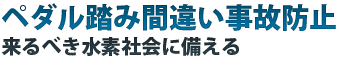














トラックバックURL